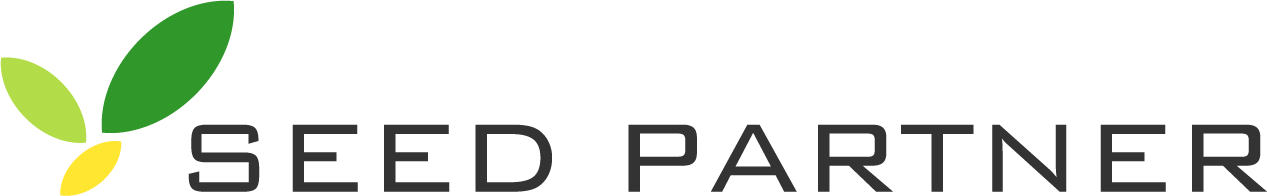ゼロからイチを生み出す頭脳!石塚氏が語る企業課題の突破法

シードパートナーでは、各分野で豊富な知見と経験を持つ顧問が、企業の成長や課題解決を支えています。本シリーズでは、第一線で活躍する顧問の方々に、これまでの歩みや支援事例、仕事にかける想いを伺っていきます。
今回ご登場いただくのは、「どんなテーマでも必ず答えが返ってくる」と評される石塚氏。企業の事業構想から社会課題まで幅広く携わり、「ゼロイチの仕掛け人」として信頼を集めています。
本記事では、その知識の広げ方や、印象に残るプロジェクトについて語っていただきました。
大学・大学院でロボット工学を専攻後、大手IT企業に新卒入社。EC事業、金融、エンタメなど幅広い新規事業の立ち上げに携わる。理系・文系双方の視点から事業を構想できるのがつよみ。独立後はコンサルタントとして幅広い業界支援を行う傍ら、教育や医療・福祉分野にも取り組む。高校で医療授業を担当するほか、視覚障がい者向け移動支援サービスの立ち上げにも参画。現在は購買・EC・事業開発コンサルを手がけ、「SAVE MONEY」「MAKE MONEY」をキーワードに企業価値の創出と社会課題の解決を両立させている。
——まずは石塚さんがシードパートナーさんのコンサルタントとして、どのような領域に携わっているのか教えてください。
石塚:担当領域を一言で表すのは難しいのですが、よく「何でも屋」と言われます。
私は大学・大学院ではロボット工学を専攻していましたが、新卒で楽天に入社し、文系職としてさまざまな新規事業やプロジェクトの立ち上げに関わってきました。そのため、理系・文系の両面からアプローチできるのが強みです。
現在はフリーランスとして、シードパートナー経由の企業支援に加え、自主的な取り組みにも注力しています。たとえば、福島県の高校で医療に関する授業を担当したり、視覚障がい者の移動支援サービスの立ち上げに関わったりしています。
楽天時代には、EC事業だけでなく、銀行・証券、エンタメ系サービス、楽天ポイントカードなど、幅広い分野の立ち上げに携わっていました。その経験から、業界や業種を問わず、さまざまな事業支援に対応できる自信があります。
ご紹介いただいて関わっている企業の一つに、A社があります。
現在、同社では大きく2つのテーマに取り組んでおり、それらをサポートしています。
1つは、「ドアのサイネージ化」です。今後、ドアに広告機能をもたせる取り組みが進むと予想されています。そこで、ドアに映像を表示させる技術の開発や、特許戦略、事業構想づくりを支援しています。
もう1つは、社員の方向けのプログラミング教育です。私はロボット工学を学んでいた背景もあり、基礎的なプログラミング講座を社内で担当しています。
また、フリーズドライ食品メーカーのB社のEC支援にも携わっています。こちらは広告施策に留まらず、「自社の強みは何か」「どこで他社と差別化すべきか」といったブランドの本質に踏み込んだ提案を行っています。単に売上を上げる施策ではなく、自社の価値をきちんと伝えられるEC戦略を設計することを大切にしています。
永沼:当社で企業の課題をヒアリングする中で、「社長のブレーンとして事業の構想を練る人が必要だ」というフェーズに入っている場合、石塚さんをご紹介することが多いです。
どんなテーマにも即座に返答してくれて、「石塚さんに聞けば、必ず何かしらの答えが返ってくる」と、企業の皆さんから信頼を寄せられています。あるお客様からは「石塚GPTが欲しい」と言われたほどです(笑)。「石塚さんの脳は宇宙空間だ」というクライアントの社長もいます。
最初は一部署の顧問として入っても、気づけば社長の右腕のような存在になっているケースがほとんどです。
石塚:どんなテーマにも対応できますが、自分の中で特に得意なのは「ゼロからイチをつくること」です。既存の仕組みを改善する「イチからジュウ」ももちろん対応可能ですが、強い関心やモチベーションが湧くのは、世の中にまだ存在しない新しい仕組みを生み出すことですね。
たとえば、医療や福祉の分野では、ビジネスとして成り立たせるのが難しいテーマも少なくありません。こうした分野は、報酬を得られないからこそ、専門職以外の人が関わりづらい現状があります。だからこそ、私は無報酬のボランティアとして関わり、新しい仕組みをつくる取り組みを行っています。
永沼:石塚さんは医療や健康分野の知識も豊富なので、食品メーカーさんと面談した際にも、「この栄養素を活かした商品なら、高単価で差別化できますよ」と、契約前の段階から具体的な提案をしてくれます。
専門的な知見をもとに説得力のあるアイデアを提示できるので、先方の担当者も「ぜひこの人と一緒にやりたい」と、その場で決断されることも多いですね。

——石塚さんの知見は、どうやって広げてきたのでしょうか?これまでの経験で培われたものですか?
石塚:大きく分けて2つの源泉があります。ひとつは、膨大なボランティア活動です。実は、ボランティアが「営業ツール」でもあり、「学びの場」でもあるんです。
私は体調を崩しやすく、自分の将来に不安を感じたことがきっかけで、550人規模の医学部生向けコミュニティを立ち上げました。コロナ禍中、そこでは週7回、無料でオンラインの医療授業を開催していました。
当時の私は医療の知識はありませんでしたが、書籍やネットで情報収集し、医師に直接連絡して無料講演を依頼。さらに、その先生から次の講師を紹介していただくという流れで、1年半ほど活動を継続しました。
その間、私はすべての授業に参加していたので、自然と医療知識が蓄積され、医療関係者との人脈も広がっていきました。
もうひとつは、「知識への強い欲求」です。私はスケジュール管理は苦手ですが、「自分の知らないことがある状態」が好きではないんです。
Zoom会議が3つブッキングしてしまった場合でも、左右の耳で別のイヤホンをつけて同時に参加していたこともあります(笑)。
それぐらい、自分の知識を増やすことに全力を注いでいます。
また、起業から数年後に、全財産を投じて、学生が無料で使えるシェアスペースを渋谷に立ち上げたこともあります。そこにはさまざまな企業の社長が遊びに来て、学生と直接話す機会が生まれるなど、貴重なコミュニティとなりました。
普段は聞けない話をリアルに聞ける環境が、自分の知見の土台になっています。
——お話を伺っていると、ものすごい行動力をお持ちだと感じます。学生時代からそうだったのでしょうか? それとも、楽天入社後に変化があったのでしょうか?
石塚:実は、ここまでの行動力がついたのは独立してからなんです。大学時代はあまりモチベーションもなく、特別何かに打ち込んでいたわけではありません。
楽天時代はとにかく働いていました。かなり長時間労働していましたが、それはあくまで「社内での仕事」であって、社外で新しいことを起こすような行動力ではありませんでした。本格的に「自分の意思で動く」ようになったのは、独立してからですね。
例えば、会津の有機農業を行う農家さんと話をしていたときのことです。
「有機農業が栄養価にどう影響するか」というエビデンスが世界的にも少なく、研究が進んでいないという相談を受けました。
私はその話を聞いてすぐに東京女子医科大学の教授に連絡を取り、「この課題を解決できる方を紹介してください」と相談しました。
すると、新潟薬科大学に専門の方がいらっしゃると聞き、「それならすぐに会いに行きます」と、その場でアポを取りました。
当然、どこからも資金が出るわけではないので、往復の交通費も自腹です。それでも「解決したい」と思えば、迷わず動きます。即行動、即対話。それが私のスタイルですね。
——改めて、シードパートナーとの出会い、パートナーとして活動するまでの経緯を教えてください。
永沼:石塚さんと最初に出会ったのは、もう7~8年前になります。当時、石塚さんが学生向けの無料シェアオフィスを自費で運営されていると聞いて、「すごい人がいる」と紹介され、お会いすることになりました。
正直なところ、最初は「何を考えている人なんだろう?」という印象でした(笑)。学生のために、全額自己負担でオフィスを提供しているって・・・本気で意味が分からなかったですね。
そのときは雑談をして、お互いの活動を紹介し合っただけで終わったんです。
それから1年ほど経った頃、ある企業の課題解決に取り組む中で、当社内にそのテーマを任せられる人材がいなかったんですね。ふと「そういえば、以前会った石塚さんなら対応できるかも」と思い出して連絡を取りました。
結果は予想以上。企業の中で大活躍してくださって、「こんなすごい人だったのか」と驚いたのをよく覚えています。
——石塚さんから見た永沼さんの印象は覚えていらっしゃいますか?
石塚:よく覚えています。失礼な言い方になってしまいますが、当時は「なんでこの人、自分に会いに来たんだろう?」と本気で思っていました(笑)。
楽天に在籍していたときは、企業の看板があったので多くの方とお会いできましたが、独立して間もない頃は、そんな立場でもなかったですから。自分に会いに来てくれるなんて不思議だな、と感じました。
永沼:お互い「なんだろう、この出会い?」と思ってたんですね(笑)。
石塚:でも、その後は永沼さんを通じて多くの方とつながり、いろんなビジネスやプロジェクトに関わりました。今ではどんな方が相手でも、まったく臆することなく飛び込めます。

——これまでに携わった具体的な案件について、印象に残っているものはありますか?
石塚:A社の支援には6〜7年ほど関わっています。
相談内容は時期によって変化していて、たとえば初期段階では「社員がもっと自由にアイデアを出せる風土をつくりたい」という依頼でした。1年ほど取り組んで風土改革に一定の成果が出たあと、新たな課題が出てきて・・・というように、継続的にアップデートしながら伴走しています。
なかでも印象的だったのが「商流の構造的な問題」です。
建物のドアは建築プロジェクトの中でも発注が最後の方になることが多く、発注元であるビルのオーナー → ゼネコン → サブコン → ガラス・サッシ商社 →ドア会社というように、何重にも下請け構造が挟まっています。
ガラスなどと比べてドアの数量は少なく、かつ発注価格も限られるため、利益が出にくい構造なんです。しかも、多くの場合はメンテナンス契約にも至らず、1回の納品で終わってしまいます。
このような「商流上の利益構造」と「ブランドリスク」の両方に対して、私は提案を行いました。そのひとつが「マーケティング機能を持たせたドア」の構想です。
例えば、ドアを通過した瞬間にスマホでクーポンが届いたり、ゲームのアイテムがもらえたりすれば、人はそのドアをくぐりたくなりますよね。
飲食店であれば「入店=来店=消費」につながるため、店舗側にとってもメリットが大きくなります。いわゆるサイネージ広告としてドアを活用するということです。
こうしたサイネージ広告が可能なドアの特許をA社と共同で取得しています。さらに、この仕組みを使うにはメンテナンス契約が必須条件となる設計にすれば、サブスクリプション的な継続収益モデルも実現できる。
ドアが売上に貢献する存在になれば、ビルオーナーが直接発注したくなる可能性も高まります。
業界3位のA社が1位・2位の企業に対して差別化を図るうえでも、非常に重要な資産になると考えています。
——こういった画期的なアイデアは、企業側が最初から求めていたものだったのでしょうか?
石塚:いえ、企業側はそこまで明確な課題としては認識していませんでした。
「うちの商流はこうなっている」と事実を共有され、その説明を受けて、「この構造にはどんな課題が潜んでいるか」「将来的にどこがボトルネックになるか」といった分析を行い、課題と向き合って解決策を提案しています。
企業側がはっきりと課題を把握している場合もあれば、「なんとなくうまくいかない」という段階からご相談いただくことも多いです。どちらでも構いません。どんなフェーズでも対応できます。
——企業側が気づいていない課題に、石塚さんが気づいて引き出しているということですね。
永沼:そうなんです。最初は「この課題を解決したい」と明確に依頼されることが多いですが、石塚さんと対話していく中で、企業自身が気づいていなかった重要な課題が見えてきます。
そうすると自然と話が広がり、「この人にもっと関わってもらいたい」となって、支援が長期化していくんです。
企業には解決すべき経営課題がいくつもありますが、すべてを同時に取り組むことはできません。だからこそ、優先順位の高いものから順に潰していく必要があります。
経営インパクトが大きい課題ほど、早期に解決することが重要です。石塚さんはそうした見極めと提案が非常にうまいので、私も安心してお任せできています。
石塚:BtoBのマーケティングって、本当に難しいんですよ。なぜかというと「商流が固まってしまっているから」です。
たとえば、ドアのような建材は代理店や商社を経由して納入されるケースが一般的です。もしその商流を変えようとすると、既存の代理店との関係が悪化しかねません。そして、代理店を失えば会社の売上が一気に落ちてしまうリスクもある。
だからこそ「商流を変える」という選択肢があったとしても、どう進めるか、どう関係者との摩擦を避けるか――そのプロセス設計が非常に重要になります。
永沼:インパクトが大きかった案件の一つが、C社です。
彼らは「屋外広告」を手がけている会社で、非常にオールドな媒体ですよね。だからこそ、「このままでは先細りしてしまう、新たなビジネスモデルを構築しなければ」という相談をいただきました。
石塚さんにファシリテーションをお願いし、2か月間で3回の企画会議を実施。私も参加させてもらいました。C社の参加者5名と私の合計6名で議論し、たった3回で30のビジネスアイデアが出てきました。
最終的に、その中から2つに絞り込むことができて、私自身も「これはいける」と思える手応えのある案が出ました。
普段はアイデアを出すタイプではないのですが、石塚さんのリードがあると自然と発想が広がって、私も5つほど案を出すことができました。
石塚:「ビジネスアイデアって、突然ひらめくもの」と思われがちですが、実はそうではありません。ある程度ロジカルに、再現可能な形で生み出せるんです。
重要なのは、自分の中に“引き出し”を用意しておくこと。そして、それをどのように整理し、必要なときに取り出せる状態にしておくか。私は整理整頓が苦手ですが(笑)、アイデアや知識に関しては頭の中でしっかり整理できています。
さらに、出てきたアイデアを「どう実現に結びつけるか」の分析も重要です。
ある程度のフレームや思考法を活用すれば、どのアイデアがビジネスとして成り立つかも見えてきます。
ただし、最大の課題は、そのアイデアを“誰が実現するか”なんです。ゼロイチでサービスを立ち上げるには、あらゆる人脈や資源を活用する力が求められます。
一般企業の部長レベルでは、人脈にも限界がありますが、私は個人事業で代表も務めているため、「社長」という立場でいろんな方に会うことができました。そのネットワークを活かすことで、ゼロイチの実現に近づけています。
永沼:C社からは、別のプロジェクトとして「防災機器に関するマーケティングレポート」の作成依頼もいただきました。リサーチ会社ではない当社に届いた依頼だったので最初は驚きましたが、石塚さんに相談したところ、見事なレポートを仕上げてくれました。

——それは石塚さんご自身が作られたんですか?
石塚:このプロジェクトは、経済産業省所管のNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が支援していた研究案件でした。X大学とY大学(双方、有名国立大学)が、防災用関する共同研究を行っており、C社が監督者を務めていたんです。
NEDOの助成金を継続して得るためには、3年間の研究成果をレポートとしてまとめる必要があったのですが、専門性が高すぎてC社の担当者では対応が難しく、時間もなかった。それで私のところに依頼が来ました。
私はロボット工学のバックグラウンドがあるので内容はある程度理解できましたし、国立防災研究所の元課長や、防災関連機器メーカーにも直接ヒアリングを行い、最終的に約120ページの報告書にまとめました。
——案件の中で印象に残っている出来事や成果が出た案件はありますか?
石塚:成果としてわかりやすいのは、やはり売上の伸びですね。
B社のEC支援では、売上に明確な変化が出ました。ECは結果が数値に表れるので、実績として見えやすい分野です。
具体的には、「LTV(ライフタイムバリュー)」──1人のお客様が生涯を通じて企業にもたらす利益──を算出するためのロジックを構築し、それに基づいてマーケティング施策を設計しました。
ツールを導入する予算がない企業も多いため、自作でPythonを使って計算プログラムを組んだり、最近ではExcelのマクロで自動化できるようにしたりと、低コストでの支援も行っています。
永沼:石塚さんのすごいところは、目の前の売上アップだけではなく、事業そのものをどうつくっていくかを常に考えている点です。
たとえば、D社との取り組みでは、機械修理専門プラットフォームの立ち上げを目指していました。ただ、当初の事業モデルのままだと、投資回収の見通しが厳しくて・・・
そこで石塚さんが複数の代替モデルを提案してくれて、「それなら実現可能かもしれない」と思える形に整えてくれました。
石塚:私が重視しているのは、「その業界の常識だけで物事を考えない」ことです。
たとえば製造業なら、製造業の中だけで課題解決しようとすることが多い。でも、そこに異なる業種や分野の視点を取り入れると、まったく新しいビジネスの形が見えてきます。
他業界の知見を掛け合わせることで、競合他社には真似できない独自性が生まれます。
短期的な売上アップを狙うこともできますが、それよりも「他社が追いつけないポジションを築く」。それが私の得意分野ですね。
永沼:すでにスタートしているプロジェクトもあります。対象となるのは、板金や塗装、加工などを手がける“ものづくりの下請け企業”です。
現在のような下請け構造のままでは、将来にわたって安定した事業継続が難しいという課題感があり、新しいビジネスモデルの構築に取り組もうとしています。
幸い、社長が非常に行動力のある方なので、石塚さんのアイデアと社長の実行力が組み合わされば、面白い展開が生まれそうです。今後の成果に期待しています。
石塚:この案件では、既存の“受注ありき”の構造そのものを見直す必要があると考えています。
多くの製造業は「どこかから仕事が振られて初めて売上になる」という構造に依存しており、自分たちではコントロールできない部分が大きい。
そこで今回は「to C(一般消費者向け)に直接商品を届ける」ことを視野に入れ、上流の不安定な商流をバイパスできるモデルを検討しています。
あわせて、楽天時代に手がけていたブランディングの知見を活かし、企業の認知や価値の再設計にも取り組む予定です。
たとえば、その企業があるのは神奈川県の秦野市という場所。工業団地内に複数の工場が集まっていて、大型トラックの往来など、地元住民に多少の負担がかかっている可能性もあります。
そこで、地元への“還元”をテーマに、地域イベントやコミュニティ形成の構想を提案しました。
たとえば「秦野工業団地まつり」のようなイベントを立ち上げる案です。実行主体は企業単体ではなく、一般社団法人を設立し、団地内の企業から年間30万円程度の拠出金を募る形で実施します。
地域の子どもたちに向けた工場見学や体験ワークショップなどを通じて、「地元に応援される企業」になる。その結果、採用力の向上や商品販売への波及も期待できます。
こうした発想は、製造業の中だけにいてはなかなか出てきません。他分野の知識や仕組みを掛け合わせることで、新しい価値の創出が可能になると思っています。

——シードパートナーとして、今後の展望をお聞かせください。
永沼:石塚さんは、普段から多くのボランティア活動に取り組まれています。だからこそ、彼がそのライフワークにしっかりと時間を割けるように、私たちがビジネスとしての収益源を確保する役割を担いたいと思っています。
もちろん、石塚さんがもっとビジネスに時間を割いてくだされば、一緒にできることはさらに増えるかもしれません。でも、今のバランスが石塚さんらしい働き方なのかなと思っていて。
私たちは、彼の活動を支える“土台”でありたいと考えています。
——石塚さんとしては、どのような仕事やつながりが広がっていくことが理想ですか?
石塚:私自身、社会課題の解決に強い関心があります。特に、「お金がないから解決できない問題」に対して、自分の力を使って何とかしたいと思っています。
もちろん、私個人はたいして資金を持っているわけではありません。でも、いただいた仕事で得たお金を、課題解決のために惜しみなく使っています。
なので、CSRの一環として「社会を良くする活動にもつながるなら」とご依頼いただけると、とても嬉しいですね。
私は貧しい家庭で育ちました。その経験から「お金持ちになりたい」という欲求よりも、「知識がなくて不幸になる人を減らしたい」という想いが強くあります。
だからこそ、教育をベースに、そこから経済・医療・福祉といった分野にアプローチして、地域に根ざした仕組みづくりをしていきたいと考えています。
永沼:私は、石塚さんのようにボランティア活動に積極的に関与しながら課題を解決していくタイプではないかもしれません。でも、だからこそ、間接的にでも応援したいという気持ちは強く持っています。
——最後に、悩みを抱える企業へメッセージをお願いします。
石塚:企業が抱える課題には、社内で気づけるものもあれば、外からの視点がないと見えないものもあります。どちらの場合でも、気軽にご相談いただければと思います。
その業界の中だけでは解決が難しい問題も、他業界の知識や人脈を活用することで突破口が見えることもあります。
「新しい取り組みに挑戦したいけれど、どう動けばいいかわからない」といった企業さんは、ぜひお声がけください。
永沼:新しい価値を生み出すには、自社の中だけでは持ち得ない知識や経験が不可欠です。
私たちがご紹介するパートナーは、どなたも自信を持って推薦できる方ばかりです。石塚さんのようにビジネスモデルに精通した方もいれば、弊社の技術顧問として活躍する元大手電機メーカーの天才的な技術者もいます。
必要なのは、「使いこなす力」です。顧問やコンサルタントは、経営の“道具”です。必要なときに必要なだけ使っていただき、不要になれば手放して構いません。
石塚さんが言っていたように、「1ヶ月だけ知見をもらい、自走できるようになればそれが理想」。
そんなふうに、顧問を“成果につながるツール”として、ぜひ活用していただければと思っています。