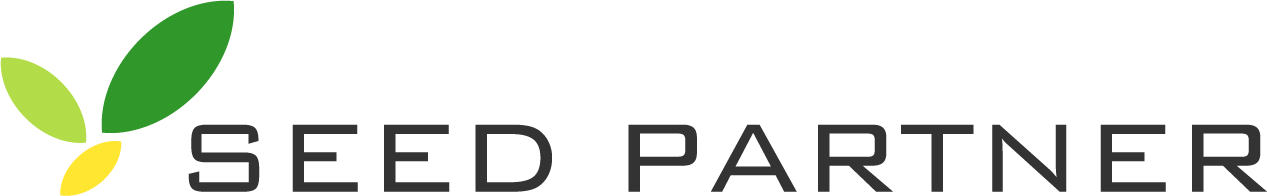営業コラム Vol.004「最低限押さえておきたい!8つの心理学テクニック」

営業において心理学を活用すると聞くと、どこか難しそうな印象を持つ人も多いかもしれません。ネットや書籍で紹介されている情報も多く、逆に何をどう使えばいいのか分からないと感じた経験はありませんか。
実際のところ、心理学の知識すべてを使いこなす必要はありません。大切なのは、営業現場で頻繁に登場する場面に対応できるようになることです。それだけで、成果につながる商談の7〜8割は十分にカバーできると考えられます。
今回は、営業の現場でよく使われる実践的な心理学テクニックを8つに厳選。どのような場面で、どのように活用できるのかを、会話の流れや提案手法に組み込む形で解説していきます。
心理学テクニックが営業で効果を発揮する理由
営業における心理学とは、相手を操作するような技術ではなく、相手が納得して意思決定を行えるよう支援するための考え方です。
多くの商談では、相手が本音を言いづらかったり、決断に迷っていたりする場面が頻繁にあります。こうした状況で、質問の仕方や声のトーン、話す順序を少し工夫するだけで、相手の気持ちを整理しやすくなり、本心を話しやすい雰囲気をつくることができます。
つまり、心理学テクニックは信頼関係の構築やスムーズな意思決定の促進に役立つものであり、単なるテクニックにとどまらず、商談全体の質を高める手段として活用できます。
実践で活用できるテクニックを厳選して身につける
心理学に関する営業ノウハウは非常に多岐にわたりますが、それらすべてを覚えようとする必要はありません。大切なのは、営業の現場で繰り返し登場する場面に絞って、そこに対応できるスキルを磨くことです。
たとえば、次回アポイントの調整、クロージングの場面、価格や時期の打診、相手の本音を引き出すヒアリングなど、営業において重要なポイントは限られています。
そこで使える心理学テクニックに集中して習得することで、商談全体の中でも特に成果につながる部分を効果的に強化することができます。
商談の流れを変える8つの心理テクニック

ここからは、これまで紹介してきた「心理学が営業に効果を発揮する理由」を踏まえ、実際の商談で使える心理学テクニックを8つ紹介します。
いずれも現場で再現性の高いスキルばかりであり、場面ごとの使いどころを意識すれば即実践に活かせる内容です。信頼を得ながら、相手の行動を促す提案をしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
01. ダブルバインド(二者択一)
相手に対して「導入しますか、しませんか」というストレートな問いかけをすると、構えてしまったり、断りやすくなってしまったりする場合があります。こうした場面では、「このサービスを導入する場合、スタンダードとプレミアム、どちらのプランが合いそうですか」など、どちらかを選ぶ形式の質問に切り替えることで、会話の主導権を自然に保つことができます。
ダブルバインドは、大きく分けて、「日程打診」「ヒアリング」「(テスト)クロージング」の3つの状況において活用できます。
日程打診
日程打診でダブルバインドを活用することは、多くのビジネスマンがご存じかと思います。初回営業でヒアリングが終わり、次回訪問で提案書を持参することになった場合、「次回はいつにしましょうか?」「次回は来週水曜の10:00でいかがですか?」と聞くのではなく、「次回は来週火曜の午後と、水曜の午前ではどちらがよろしいですか?」と選択肢を提示するとアポがとりやすくなります。
アポがとりやすくなる理由は、主に2点あります。
まず、「AとBとどちらにしますか?」と問いかけると、通常の会話の流れが選択肢を選ぶことになります。「次回のアポはいつにしましょうか?」「次回は〇〇日でいかがですか?」と聞くと、相手から「来月でいいですよ」「また、こちらから連絡します」と言われやすくなります。
あらかじめ選択肢を提示しておくことで、別の選択肢を考えさせないようにするのです。
続いて、選択肢を出しているのはこちらですが、最終決定をするのは相手。つまり、こちらでスケジュールをコントロールしながら、相手を尊重している状況になります。相手が決めている状況を作るので、アポのキャンセルを起こしにくくなる効果もあります。
ヒアリング
課題のヒアリングにおいて、「貴社の課題は何ですか?」と直接的な質問をすると、回答が返ってこないか、返ってきても本質的な課題ではないケースが多くなります。初めて会った相手(営業担当)に、自社や自身の恥(課題)をさらけ出すことは少ないです。また、自社や自身の本質的な課題を把握していない場合も珍しくありません。
「営業準備」にて想定した相手の課題を提示すると、相手の頭の整理がしやすいです。「貴社の業界の一般的な課題はAとBですが、貴社はどちらか、または双方に課題を感じていますか?」と選択式の質問をすると、一気に回答しやすくなります。
相手の回答は「当社は特にAに課題を感じています」や「A、Bどちらも課題です」または、「A、Bどちらも課題ではありません」のどれかになるはずですので、その後に課題に関する議論を発展させることができます。
「A、Bどちらも課題です」と回答があれば、より重要な(優先度の高い)課題を議論によって抽出することで、当該企業の最優先の課題が選定できます。「A、Bどちらも課題ではありません」と回答があれば、他では「C、Dの課題が考えられますが、そちらは課題になりますか?」とさらにダブルバインドの質問を出します。
他の課題がない場合はそこで、「貴社では業界の一般的な課題はクリアできているのですね。では、どんな課題が社内で話題に挙がっていますか?」と聞くことができます。
(テスト)クロージング
提案が終わり、商談の後半に入った時に、相手が自社のサービスに興味を持っているか?まだ懸念や不安があるか?を確認する必要があります。
その際に、テストクロージングとして、ダブルバインドが有効活用できます。
プラン(料金)の選択
AプランとBプランでしたら、現時点ではどちらになりそうですか?
時期の選択
このサービスの導入を行うのであれば、今すぐになりますか?
それとも、予算を組み直す来期になりますか?
決裁権の選択
このサービスの導入は〇〇さん(目の前の商談相手)が決定しますか?
それとも、〇〇さんの上司になりますか?
上記の質問に対する回答によって、相手の本気度が分かりやすくなります。「AプランとBプランどちらですか?」と質問をした際に、採用を現実的に考えていれば「Aプランです」「Aプランで社内検討を進めています」といった回答が返ってる可能性が高くなります。
まだ悩んでいる場合、不安・懸念が解消できていなければ、「まだ、プランを決める状態ではありません」「そうですね・・・(無言)」などのような回答になります。まだプランを決められる状態でなければ、相手の不安や懸念を聞き出し、それを解消する必要があります。
相手に質問をする場合は、原則選択式にすることをおすすめします。ただ、選択肢を提示する場合には、こちらの準備が必要です。逆にいえば、しっかり「準備」をしていれば、選択式の質問をしやすくなります。
選択式の質問ができれば、商談をコントロールしやすくなります。(あくまで商談のコントロールです。買う・買わないのコントロールは商談相手が決めるものです。)
02. 動作訴求法
人の心理は言葉だけでなく、視覚的・身体的な動きにも大きく影響されます。営業の場面では、手帳を開く、資料を差し出す、契約書をテーブルに置くといったシンプルな動作が、相手の意識や態度を変えるきっかけになります。
次回訪問の日程を決める際に、何も言わずに手帳を取り出すだけで、相手も無意識のうちに「今はスケジュール調整のフェーズなのだ」と感じ取ります。
また、クロージングの場面では、契約書をテーブルに出しておくだけで、「今日は契約について判断する場なのだ」と相手に伝わりやすくなります。
このように、行動によって相手の意識を自然に導くことで、強引さを感じさせずに商談を進めることができ、営業担当の立場からしても無理のないクロージングのタイミングをつくることができます。
03. オフビート
商談前のアイスブレイクや、商談が一通り終わって雑談に入ったタイミングは、相手の緊張が解けて本音が出やすくなる貴重な時間帯です。
このフェーズでは、商談中には話しづらかった内容や、相手自身が整理できていなかった課題が自然と口に出ることがあります。たとえば、「さっきの提案、実は社内で引っかかっているのが予算の部分でして・・・」といったような本音が、商談終了後の立ち話で明らかになることは少なくありません。
このオフビートの時間を単なる雑談で終わらせず、相手の口が開きやすくなるように会話を続けることで、ヒアリングでは聞き出せなかった重要な情報を得ることができます。
「最近、御社内で注目されているテーマや課題感はありますか」など、自然なトピックで話を続けることで、次の打ち手に直結するヒントをつかめる可能性が高まります。
アイスブレイクの目的や効果的な話し方については、前回の営業コラムも参考にしてください。
04. メラビアンの法則
営業においては、話す内容そのものよりも、「どう伝えているか」によって印象が大きく左右される場面が多く存在します。メラビアンの法則によると、人が他者から受け取る印象は、資格情報、聴覚情報、言語情報となり、割合は以下の通りとなります。
- 55%は視覚情報(見た目や表情)
- 38%は聴覚情報(声のトーンや話し方)
- 7%のみが言語情報(話の中身)
割合をみると、話の内容は人の印象の7%しか寄与していないことになります。
清潔感のある身なりをすることは言わずもがなですが、相手が聞きやすいようにハキハキ話す、大事な話はゆっくり話す、など、相手が理解しやすい話し方を意識することもとても大事です。
また、メラビアンの法則とは異なる視点ですが、提案の冒頭に結論を明確に伝えずに話し始めてしまうと、聞き手は意図をつかみきれず、理解や共感が得られないまま話が進んでしまうリスクがあります。
初回でヒアリングをして、提案書を持参した2回目訪問の冒頭で、「今回は前回▲▲さんからお聞きした◯◯という課題に対して、3つの提案をご用意しています」と前置きを加えると、相手の商談への集中力が増す効果が期待できます。
05. 他者の影響力(事例)
自社サービスの価値を伝えるときに、「このサービスはおすすめです」と主張しても、相手には主観的な営業トークと受け取られることが多くあります。その際に有効なのが、「事例」を通じて伝える方法です。「事例」とは、自社のサービスが他のクライアントの役に立った成果です。
同業種の企業で同じような課題を抱えていた顧客が、導入後にどのような成果を得られたのかを具体的に示すことで、相手は自分事としてイメージしやすくなります。
事例は「業種、企業規模、課題、サービス内容、成果」を順を追って話すことでリアリティが増し、サービス活用のイメージを持ってもらいやすくなります。
以下は、弊社クランアントで本当にあった事例をもとに、相手への伝え方の一例をご紹介します。
事例 その1
| 業種、企業規模 | 売上約5億円の製造業が、 |
| 課題 | 生産工程におけるロス(廃棄)が多く、生産コストが高止まりしていた。 |
| サービス | そこで、当社の生産現場改善を得意とするコンサルタントが支援に入ったところ |
| 成果 | 活動初日の改善で月間40万円のロスを削減することができました。 |
事例 その2
| 業種、企業規模 | 社員100名の大手企業子会社の屋外広告の事業部が、 |
| 課題 | 15年連続で売り上げがダウンしていました。営業数と成約率の課題の他に、単に屋外広告を案内するだけの営業方法に限界を感じていました。 |
| サービス | そこで、当社の新規事業の創出、および実行支援を得意とするコンサルタントが新規事業創出のプロジェクトを行ったところ、 |
| 成果 | 先方のメンバー5名から、2か月間で30件の新規事業アイデアを創出することができました。また、その中から2つのアイデアを実行に移しました。 |
私が「弊社のコンサルタントはスゴい」と何度も言うより、上記の事例を話したほうがよほど納得感があると思います。
重要なのは、相手の業種や規模感、導入の背景が近い事例を準備しておくことです。相手との距離が近い具体例ほど、納得感や信頼感が増します。自社の主張ではなく、第三者の実績を使うことで、説得力を飛躍的に高めることができます。
06. スムーズな反対問答
商談の途中で相手から「当業界における事例がない(または少ない)ために不安を感じる」「この費用では社内決済が難しい」「他社と比較中でして」「少し検討させてください」といった反応が返ってくるのは珍しくありません。こうした“買わない理由”に対して、いかに冷静かつ自然に受け止めながら回答できるかが、営業としての信頼を左右します。
実際、多くの反対意見や懸念はある程度パターン化できるものであり、事前に想定と準備があれば、過度に動揺することなく返答できます。
むしろ、相手から「買わない理由」を言ってもらえれば、その不安や懸念を払しょくできれば、購入に近づくチャンスともとらえることができます。
相手の不安や懸念は「サービスの質」「自社に対する有効性」「価格」「活動開始時期」「上司の決裁」で80~90%は占められると思います。
自社の営業社員から「今までどんな反対文句を言われたか?」を集め、何を伝えることでその反対文句を切り抜けられたかという「反対問答集」を作れば、若い営業担当も商談を優位に進めることができるようになります。
私が初めてコンサルに入った広告事業では、屋外広告は「古い」「効果検証ができない」と言われて失注することが目立っていましたが、「古くても残っているのは活用意義があるから」「テレビCMをはじめ、Web広告以外は効果検証ができない」と返すことで、多くの商談がゲームオーバーにならずに先に進みました。
07. 商談は駆け引き
商談は一方的なプレゼンではなく、相手の感情や心理状態を見極めながら進める“駆け引き”の連続です。営業側が話すことだけに集中しすぎると、相手の表情の変化や違和感に気づけず、せっかくの提案が響かないこともあります。
目や耳から得られる情報を常にインプットしながら、相手が今どんな温度感にあるか、どんな不安や疑念を抱えているのかを感じ取ることが重要です。話す前に“間”を取ったり、「ここまでの内容でご不明点はありますか?」と確認を入れたりすることで、対話の主導権を握りながらも相手に寄り添った提案が可能になります。
営業の本質は、自分が話したいことを伝えるのではなく、相手が知りたい情報から会話を始めることにあります。また、相手の反応を見ずに話し続けるのではなく、表情・声のトーン・沈黙などの「非言語情報」をしっかり受け取ることが、対話の流れを整えるためには欠かせません。
このような駆け引きの姿勢を持つことで、相手の心理的な抵抗を和らげ、商談をより自然に進めることができます。
駆け引きを有利に進める最大のコツは、相手から話し始めてもらうことです。交渉は先に話を始めた(情報を提供した)人が圧倒的に不利になります。その情報をもとに会話(議論)が進むからです。
自社サービスという情報を先に伝えてしまうと、そのサービスを使うべきか?使う必要がないのか?について議論が展開されます。ただし、相手の課題が先に情報として出てくれば、その課題をどうやって解決するか?について議論が展開されるようになります。
そのためには、こちらは「質問」をすることが大事です。適切な質問をするためには「営業準備」が何より大事になります。
08. サービスの種類を見極める(課題解決型と付加価値型)
すべてのサービスが同じアプローチで伝えられるわけではありません。サービスは大きく分けて「課題解決型」と「付加価値提供型」の2つに分類され、それぞれに適した営業手法があります。
たとえば、業務効率化や採用支援など、顕在化している課題に対するソリューションを提供するサービスは、ヒアリングと問題整理を軸にした提案が効果的です。一方で、オフィスのブランディング支援や福利厚生の拡充といった、現状に明確な不満がない場合に提供するサービスでは、利用後の理想像や価値訴求を丁寧に伝える必要があります。
商談の入り口で相手の意識やニーズの段階を見極め、自社のサービスがどちらの性質を持つかを踏まえて構成を組み立てることで、より相手の納得感につながる提案が可能になります。
応用テクニックで商談力を高める

ここまで紹介してきた心理学テクニックは、商談の流れを整え、信頼関係を構築するうえで欠かせない基礎的なアプローチです。ここからは、より実践的な応用編として、アイスブレイクとプレゼンテーションスキルの活用法を紹介します。
アイスブレイクは“きっかけ”ではなく“戦略”
商談の冒頭で交わされる何気ない雑談は、実は極めて戦略的な意味を持っています。相手の緊張をほぐし、話しやすい空気をつくることで、その後のヒアリングや提案の深度が変わってきます。
話題は「最近の業界動向」「オフィス周辺の変化」「先方社員の態度、社内の書物・置物」など、相手の関心に触れやすい内容が効果的です。ただ場を和ませるだけでなく、“共通の認識”をつくることが、その後の商談の土台になります。
営業におけるアイスブレイクの効果や具体例については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
プレゼンは“構成力”と“共感力”がすべて
良い提案は、内容だけでなく「伝え方」で決まります。結論から伝える、数字で示す、話す順序を明確にするといった“構成力”に加えて、相手の理解や関心に寄り添った“共感力”も問われます。
たとえば、「このサービスは優れています」と抽象的に語るよりも、「3ヶ月で〇〇時間削減された」、「導入前と比較して〇%改善した」といった具体的数値を交えて話すだけで、相手の納得感は格段に上がります。
また、相手の業界背景やトレンドを踏まえて「なぜ今この提案なのか」を語ることで、“相手のための提案”として受け取ってもらいやすくなります。
プレゼン力を高めるために特に意識したいポイント
- 結論から話す(PREP法などを意識)
- 数字で話す(できる限り、定量→定性の順に)
- 箇条書きで整理する(複雑な内容ほど構造化)
- 周辺情報を補足する(背景・歴史・類似事例など)
- 話し方に抑揚や“間”を入れる(相手の理解を確認)
まとめ
心理学テクニックは、営業トークのスパイスではなく、商談の質と成功確度を高めるための“基礎設計”のような存在です。相手の心理に寄り添い、自然な流れで提案を受け入れてもらうためには、聞き方、伝え方、動き方など、あらゆる接点に意図を持つことが欠かせません。
すべてを一度に完璧にこなす必要はありませんが、よく使う場面から1つずつ実践に落とし込むことで、営業の再現性と成約率は確実に上がっていきます。心理学を知っているだけで終わらせず、使いこなせる高付加価値のビジネスパーソンを目指していきましょう。